

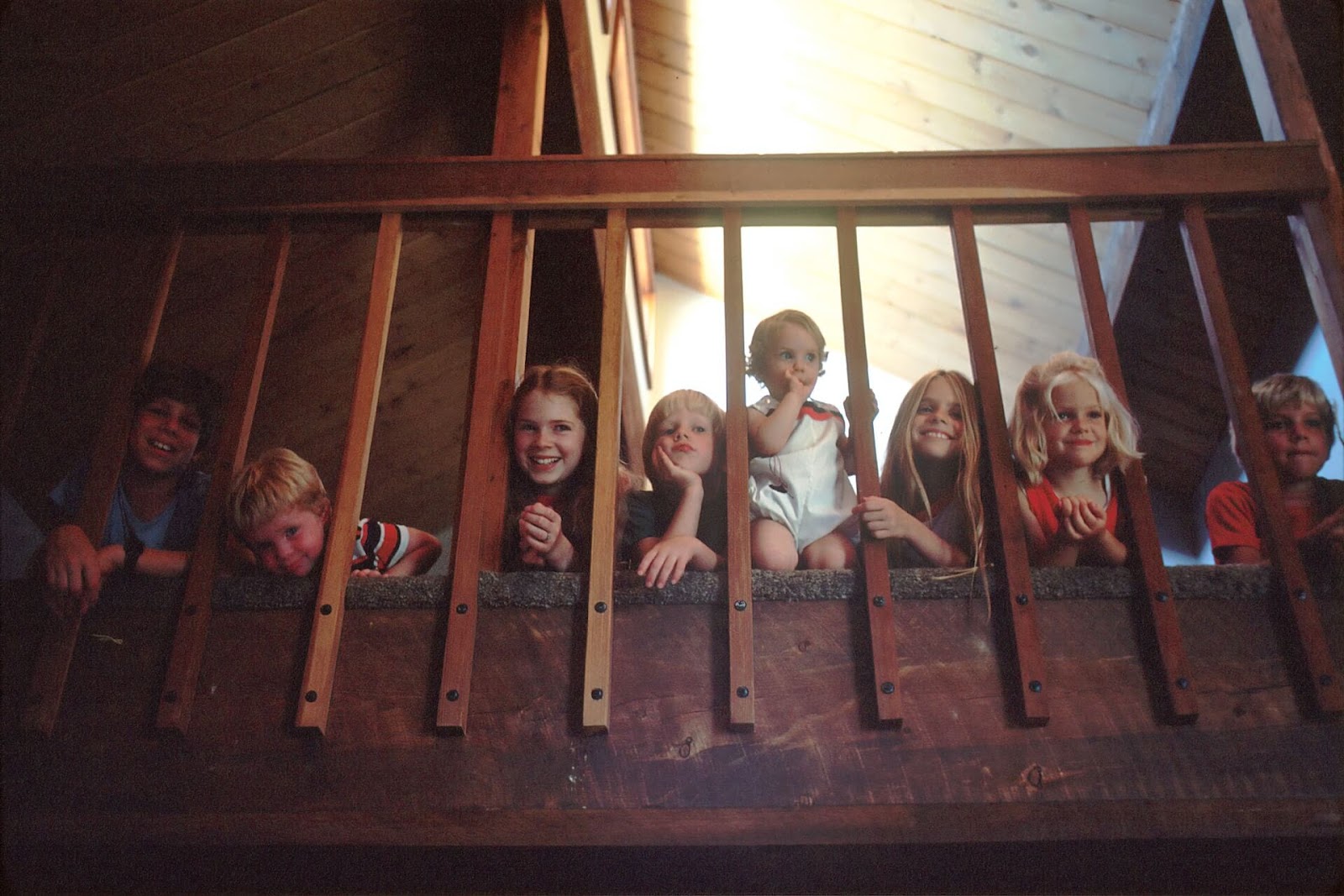
私たちは、常に他者と関わりを持ちながら生活しています。集団生活や人間関係の構築において欠かせない能力が、社会性です。社会性が高い人はコミュニケーション能力にも長けており、学校以外の場所でも友達や味方を増やせます。
今回は、社会性の意味や社会性が高い子どもの特徴、子どもの社会性を引き出す方法などをご紹介します。社会性は、社会での成功体験や自己肯定感の育成にもつながるものです。社会性の鍛え方を学び、子どもの人生をさらに豊かにしていきましょう。

社会性とは、広く社会に通用する性質です。たとえば責任感・コミュニケーション能力・協調性・社会的マナー・モラルなど、社会の一員として生きるために求められる総合的な性質を指します。
社会性と似た言葉に社交性があります。社交性とは、他者とコミュニケーションを取ったり円滑な人間関係を構築したりするための能力です。つまり社交性は社会性の一部といえます。社会性が高い人は、学校や会社などの複数人のコミュニティにおいて、メンバーの一員としてふさわしい言動ができるでしょう。

ここでは、社会性が高い子どもの特徴をご紹介します。社会性は、世の中で生きるための基本スキルでもあります。小学生時代から世渡りが上手な子やコミュニケーション能力が高い子の特徴を知り、家庭での教育につなげていきましょう。
社会性が高い子どもは、相手の気持ちを察した言動が得意です。気持ちを言葉にする前に、「この言い方は傷つけてしまうかもしれない」「誤解されないために違う言い回しにしよう」と考えられる冷静さを持っています。
相手に寄り添った言動は、自分の心に余裕があるからこそ実現できます。そのため社会性が高い子どもは、感情にのまれずに状況を客観視する力も持っているといえるでしょう。
自分の意見を堂々と相手に伝えられることも、社会性が高い子どもの特徴です。社会で関係性を構築するためには、相手と同じ目線に立った対話が求められます。
相手の意見を尊重しつつ自分の意見も伝えられ、積極的に相互理解を求める姿勢を持つ子どもは、社会で生きる力が強いといえるでしょう。

ここでは、社会性に乏しい人が陥りがちなトラブルをご紹介します。とはいえ、社会性の有無は個性ともいえます。子どもの特性に寄り添った教育を行う前提で、社会性がないことのデメリットを知っておきましょう。
社会性に乏しい人は、集団になじめずに孤独感を抱きやすい傾向にあります。集団の中で自分がどのように振る舞えばよいのかわからず、周りに合わせた言動ばかりを優先してしまうでしょう。
社会性には、周りの幸福を尊重したり空気を読んだりすることも含まれます。しかしコミュニケーションに臆病な人がいつでも周囲に合わせてしまうことは、社会性とはいえません。いつまでも自分らしさを発揮できず、誰にも心を開けなくなってしまいます。
周りと協力できないことも、社会性がない人が陥りやすいポイントです。自分の弱みを曝け出すことや、お願いして断られることを恐れており、トラブルやストレスを一人で抱え込んでしまいます。
どれほど能力が高い人でも、たった一人でできることには限界があります。周りとの協力を恐れたままでは、成長や成果の可能性が狭まってしまうでしょう。
社会性がない人は他者との関わりが少ないため、チャンスや出会いの機会も減っていきます。たとえば会社で新しいプロジェクトが発足する際、新メンバーを集めるとします。社会性がない人は普段から人との関わりが薄いため、メンバーとして想起されづらいのです。
その結果、自分より仕事の能力は低いものの社交性には長けた人が採用されるケースもあるでしょう。社会性の乏しさはチャンスを逃しやすいだけではなく、そもそも巡ってくるチャンス自体の数も減らしてしまうのです。

ここでは、子どもの社会性を磨く方法を3つご紹介します。子どもにとっての社会は、学校と家庭が大部分を占めます。学校教育だけでは十分に身につけられない社会性を、家庭教育で楽しみながら磨いていきましょう。
子どもの社会性を磨くためには、幅広い価値観の人々と交流する機会を増やしましょう。家庭や学校で交流する人は、ほとんど毎日同じ顔ぶれですよね。限定されたコミュニティ内だけの活動では、新しい価値観は養われません。
「世の中には人の数だけ価値観がある」と子ども自身が認識することで、コミュニケーションや言動に選択肢が生まれます。今まで自分が持っていなかった価値観に触れるごとに、相手に寄り添った関わり方を学べるでしょう。
チームプレーが必要な習い事も、子どもの社会性の育成に効果的です。たとえばサッカーやバスケットボール、野球などが挙げられます。自分の動きがチームにどのような影響を与えるのかを学習する中で、コミュニティにおける動き方が学べます。
論理的に正しい行動や発言でも、伝え方や言葉選びによってはネガティブな印象を与えてしまう場合がありますよね。チームプレーでは、正しさだけではなく優しさや想像力など、社会性に関わるさまざまな能力を養えるでしょう。
社会性とは、社会の一員としてふさわしくあるための性質です。対人マナーや一般常識を身につけることは、社会性の育成に欠かせません。たとえばテーブルマナーや訪問マナーなどは、学校ではなかなか教わらないものです。家庭教育の中で学習し、社会性を養っていきましょう。
とくに小学生は、アニメや漫画などの創作物の影響を受けやすい傾向にあります。フィクションでは許される表現が、現実では許されないケースも多くありますよね。お子さんのふとした言動の違和感を察知し、アドバイスを重ねていきましょう。

昨今、社会性を磨くために注目されている習い事が、プログラミングです。プログラミングと聞くと、一人でパソコンに向かっている姿を想像する人が多いかもしれません。しかし実際のプログラミングは、メンバーと積極的なコミュニケーションを取りながら進行します。
相手の言葉を正しく受け取る読解力や、自分の進捗を正しく伝える語彙力、納期を守るための計画力・自己管理力など、総合的な社会性が磨かれていくのです。お子さんの習い事に迷っている保護者様は、ぜひプログラミングを検討してみてはいかがでしょうか。

今回は、社会性の意味や社会性が高い子どもの特徴、家庭における社会性の鍛え方などをご紹介しました。社会性を養うための習い事として、プログラミングスクール「プロクラ」をおすすめします。
プロクラでは、子どもが大好きなマインクラフトの世界で楽しくプログラミングを学べます。「子どもには社会性を身につけてほしい」と考えている保護者様は、ぜひこの機会に無料体験教室や資料請求から始めてみてはいかがでしょうか。
COLUMN