


子どもたちの成長において欠かせない要素としてメタ認知が挙げられます。メタ認知とは、自己の思考や学習を理解しコントロールする能力を指します。自分を客観的に捉え、効果的な学びや行動を促す重要な認知プロセスです。
メタ認知があることで自身の能力や可能性を理解し、将来像をより具体的に描くことが可能になるのです。
この記事では小学生のお子さんをもつ保護者様に向けて、メタ認知の概要やその効果について詳しく解説します。また、メタ認知を向上させるための具体的な方法について紹介します。

メタ認知とは、端的にいえば第三者の立場で自分自身を見つめる能力です。たとえば、学習におけるメタ認知とは「どの方法を使うと自分は覚えやすいのか」や「今、どのくらい理解していて改善点はどこにあるのか」とふり返り、評価することを意味します。
近年、メタ認知は学習意欲向上の鍵として注目され、小学校高学年から中学生にかけて急速に発達するといわれています。メタ認知とは自己理解を深め、学びの質を向上させる重要なスキルであり、子どもたちの潜在能力を引き出すために不可欠です。

メタ認知には「メタ認知的知識」と「メタ認知的技能」があり、両者は互いに補完し合っています。知識だけで行動が伴っていなければ結果を出せず、行動して得た情報を蓄積できなければ成長につながりません。ここでは2つの要素について紹介します。
メタ認知的知識とは自己に関する詳しい情報を指し、具体的には以下のような要素が含まれます。
たとえば「勉強は得意ではないが走るのは得意」といった自己分析や「集中力をつけるために学習と休憩のメリハリが大切」といった理解などが、メタ認知的知識といえるでしょう。
知識をもつことで自分の良さや課題が明確になり、具体的な計画を立てる基盤が形成されます。また、メタ認知的知識は適切な行動力へとつながります。
メタ認知的技能はメタ認知的知識をもとに行動し、絶えず改善していく力を指します。メタ認知的技能は以下の2つに分かれます。
メタ認知的モニタリングは自己の状態を客観的に見つめ、最適に行動できているかチェックすることです。メタ認知的コントロールはモニタリングで得た情報をもとに、行動や感情を適切に制御するスキルを指します。2つの技能を連動させることで、効果的な学習や活動が可能になるのです。

メタ認知能力が高い人とは自己をよく理解し、強みや弱みも含めて客観的に評価できる人です。必要な対策を考えて実行に移しながら、自己を鍛える素地があるといえるでしょう。ここでは、メタ認知能力の高い人の特徴として3つの視点で解説します。
メタ認知能力とは感情に流されず、自己を客観視してコントロールする力を指します。メタ認知能力が高い人ほど感情的になることはありません。
メタ認知能力の高い人は、怒りなどの感情が湧いても、その状態を自覚し「私は今、怒っている」と客観的に気づけます。感情に振り回されず、冷静に判断することが可能です。
メタ認知能力は円滑な人間関係を形成し、仕事での成功につながる要素となります。
メタ認知能力が高い人は失敗を冷静に受け止め、その原因を分析して次に生かす能力があります。メタ認知によって、失敗や挫折を経験した際に受けるショックや残念な気持ちを引きずらず「なぜ失敗したのか」その理由を探ろうとするのです。
課題の根本的な要因を見抜き、改善点を洗い出して同じ失敗をくり返さないよう対策を考えます。メタ認知能力の高い人は、以上のアプローチを通じて仕事や勉強において課題解決能力を高め、変化の激しい社会において柔軟な対応を可能にします。
メタ認知とは自分の強みや弱みを客観的に把握し、現実的な目標を立てられる力を指します。メタ認知能力が高い人が自己分析を通じて「いざというときの集中力は高いが比較的時間にルーズである」と判断したとしましょう。この場合、次のような特徴が挙げられます。
メタ認知能力の高い人は、明確な自己分析を通じて目標を設定したり計画を立案したりすることができます。ふり返りと修正によって、強みを強化したり弱みを改善したりしながら自己を成長させていくのです。
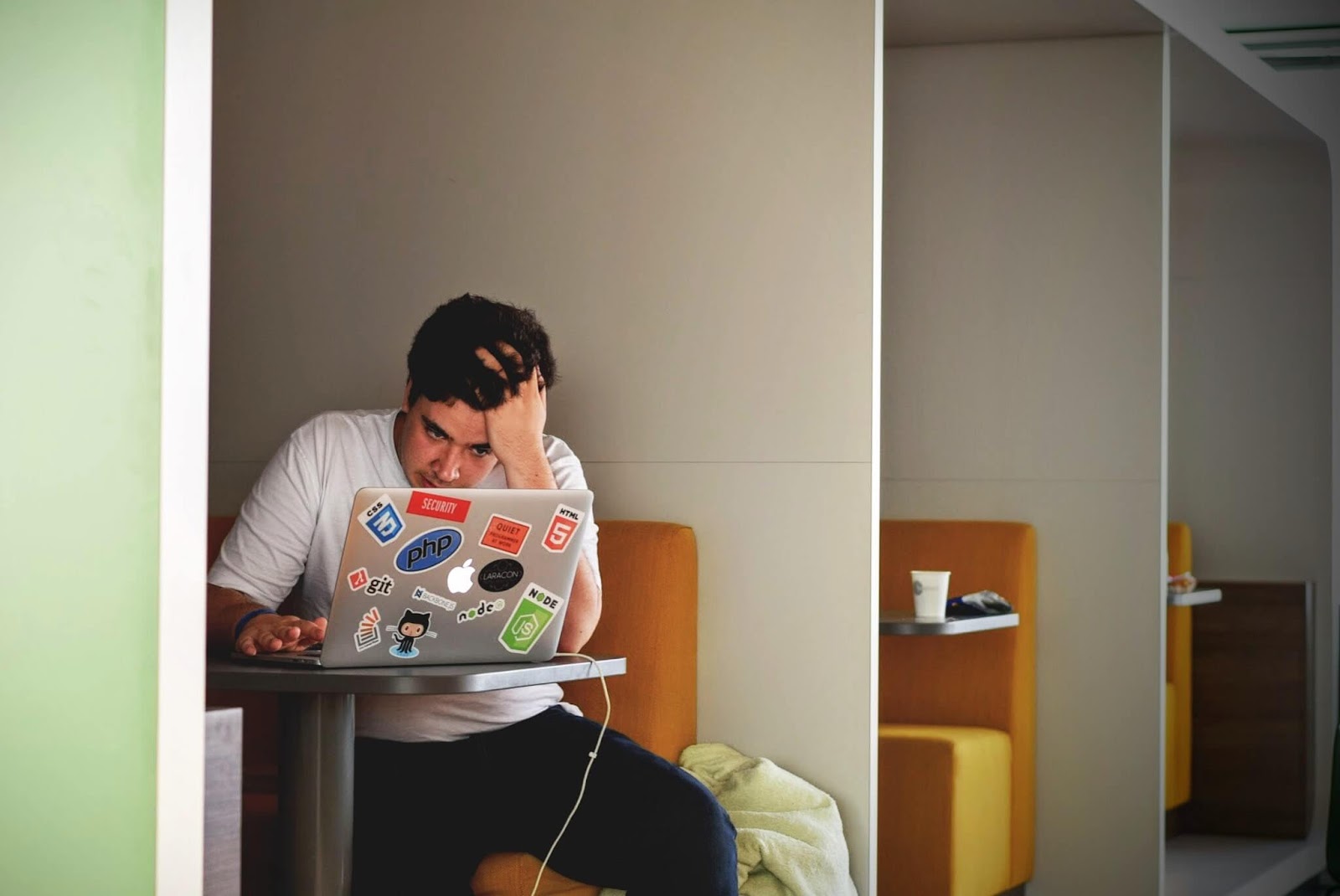
メタ認知能力が低い場合、感情を表出しすぎて他者との関係性を保てなくなる可能性があります。また、自己理解がうまく進まないため、適切な目標設定や計画立案が難しくなるでしょう。以下に、メタ認知能力が低い人の例を紹介します。
メタ認知能力が低い人は、感情的になって他者に当たってしまう傾向が少なくありません。職場における仕事のミスに対して怒りやすく、同僚や上司に対して冷静に対応するのが難しくなるでしょう。また、自分ではなく相手や環境のせいにしてしまう可能性があります。
メタ認知能力が低く、感情のコントロールがうまくいかなければ、他者の立場や意見を理解しにくくなります。その結果、人間関係に支障をきたしてしまうでしょう。メタ認知能力の向上を通じて感情の管理を強化することが重要です。
メタ認知とは自己の能力を客観的かつ具体的に把握することです。メタ認知能力が低い場合、自分の強みや弱みを把握しづらいため、目標や計画の具体性が不足してしまいます。たとえば、メタ認知能力の高い人と低い人とでは、目標設定において以下のような差が生まれるでしょう。
メタ認知能力が低い場合は目標が漠然としており、達成に向けた手順を見つけることも難しくなります。目標を実現できず、失敗や挫折だけが残る結果となり、無気力な状態に陥るかもしれません。
感情に支配されやすい傾向にある人は、外部からの刺激や状況に対して感情的な反応が強い傾向があります。この背景にはメタ認知能力の低さが挙げられるでしょう。
メタ認知能力が低い場合、感情を客観的に観察し、何をどうすれば良いのか判断するのが困難になります。ストレスやプレッシャーに屈してしまい、新たな対処法を見つけるのも難しくなるでしょう。
感情の影響を最小限に抑え、効果的な意思決定を可能にするために、メタ認知能力の育成が求められます。

メタ認知とは人間が客観的に自己分析することを通じて、自分を認め、より良く成長させるための理解力であり、行動する力であると定義できます。ここでは、メタ認知が子ども教育に与える影響について解説します。
メタ認知が子どもたちの教育に与える影響の一つは、自分に合った学習計画が立てられることです。メタ認知能力が高まると、子どもたちは学習や目標達成に向けて具体的で効果的な計画を立てられます。
たとえば、苦手な教科の克服をめざす場合、次のような流れで学習を進めていくでしょう。
このように目標を達成するために必要なポイント(計画や具体的な内容など)を洗い出し、どのように学びを進めるのか考えて行動できます。メタ認知能力は、自律的な学びの習慣づけにつながる重要な要素なのです。
メタ認知とは自己を冷静に分析する力とつながっており、この第三者としての見方が他者理解にも良い影響を与えます。メタ認知能力が高ければ、相手の状況や思考を客観的に捉え、尊重することが可能です。
メタ認知能力が高い人は「自分だったら」という視点にもとづいて思いやりのある行動ができ、異なる考え方を認める姿勢をもちます。逆にメタ認知能力が低い人は、自己中心的な様相を示すかもしれません。「自分が〇〇と思っているからAさんも〇〇と思っているはず」といった一方的な見方で捉える傾向があります。
メタ認知能力が高い場合、客観的な自己評価が可能であるため、他者との比較による劣等感を抱きにくくなります。その理由は、メタ認知が可能になれば自分の強みや弱みを正しく理解でき、それらを受け入れられるためです。
自分自身を認めている人は、他者との比較で悩まされることなく、周囲に対しても柔軟かつポジティブな態度で振舞えるでしょう。
メタ認知による自己理解は他者との関係性に良い影響を与え、他者の才能に嫉妬することなく、自分の成長に焦点を当てられるのです。
メタ認知とは自分の現状を客観視して、目標達成への具体的な手段を考えることを指します。メタ認知能力が高ければ学習面やスポーツなどで努力を積み重ね、成果を上げやすくなるでしょう。
その理由は、メタ認知能力によって具体的な目標や計画設定が可能になり、自分のやるべきことがわかって学習や練習を続けていけるからです。やり始めのころは困難さを伴うとしても、目標が明確であればあるほど努力を続けて乗り越えていくでしょう。
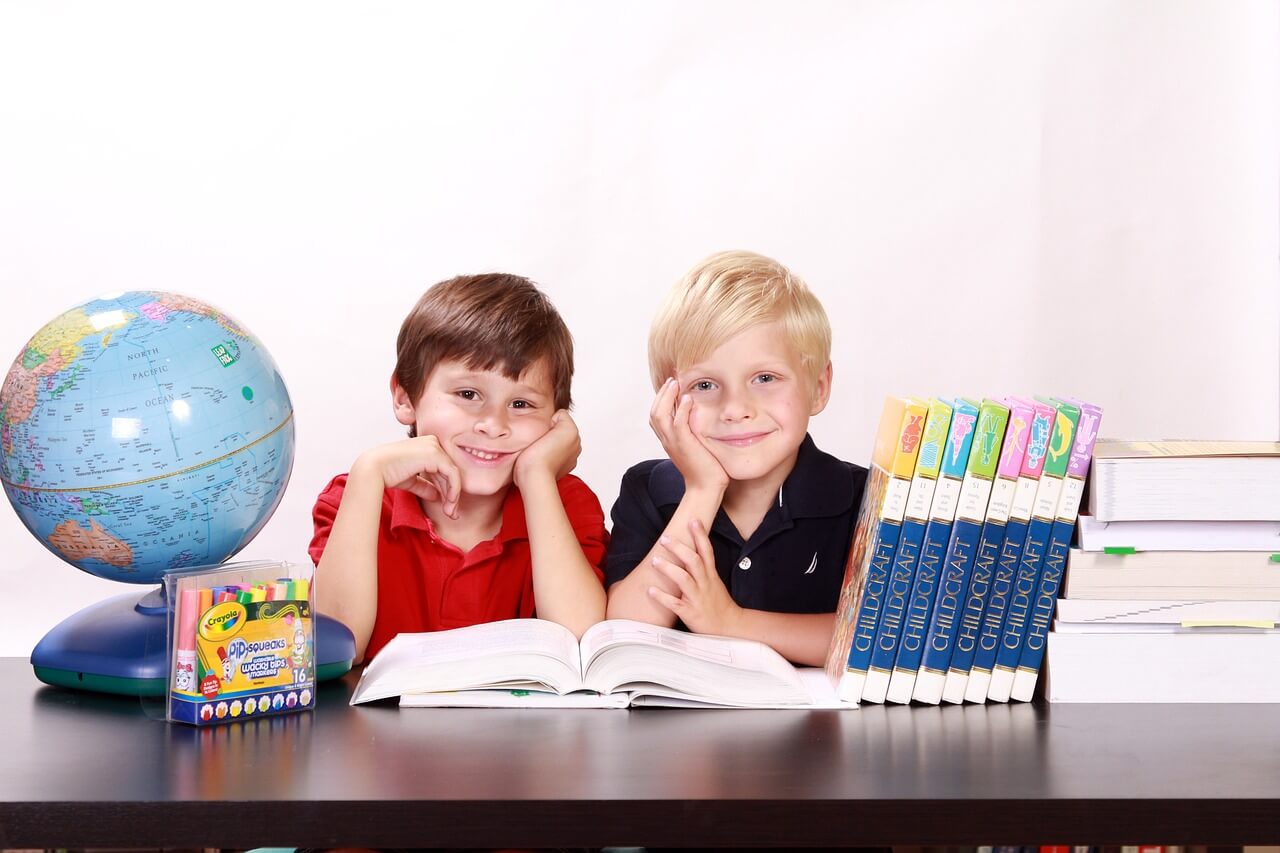
メタ認知能力は子どもたちの教育により良い影響を与えます。お子さんのメタ認知を高めるには、以下に紹介する方法を取り入れてみましょう。目標や計画設定、分析する力の育成などについて詳しく解説します。
学習計画表を作成することは、お子さんのメタ認知能力を高める重要な手段の一つです。計画表は「いつ」「どこで」「何を」「どのくらい」学習するかを具体的に示すもので、学習のスケジュールや進捗を確認するうえで重要です。
最初は予定通り進まないこともあるでしょう。しかし、その都度修正することで自己理解や自己管理スキルが養われます。計画の策定や実践の経験を通じて、お子さんは効果的な学習方法を見つけ、メタ認知能力を高めていけるでしょう。
失敗の要因を分析する習慣を身につけるのは、メタ認知の向上に役立ちます。保護者様はお子さんが失敗した際に、以下のポイントを注意して対応しましょう。
失敗やミスをした際に叱るだけでは、お子さんのメタ認知能力を高められません。失敗の要因を考えさせ、親子で分析の質を上げていくことで、子どもたちは自主性を発揮しながらメタ認知能力を向上させるでしょう。
子どもたちのメタ認知能力を育むためには、成果や過程を具体的に褒めることが大切です。具体的な褒め方とは「すごいね」「がんばったね」といった言葉ではなく、以下のような内容を指します。
単に「すばらしい」と伝えるのではなく、子どもたちの取り組む姿を具体的に示しましょう。また、成果をもたらした要因にスポットを当てる褒め方は、子どもたちが「なるほど」と納得し、メタ認知の育成を促します。
メタ認知能力を高めるためには日記をつけることが有益です。お子さんが日記を書く際は、正確な書き方を強要するのではなく、自由に表現できる環境を提供しましょう。
書き方にこだわりすぎると本音を書き出しにくく、正しい自己理解が妨げられ、メタ認知能力の向上に制約が生じます。怒りや焦りなどのネガティブな感情も手を止めずに書き綴ることで、次第に心が落ち着いてきます。
保護者様はお子さんに自由に書き連ねる機会を提供し、自己理解を促進できるようサポートしましょう。
保護者様がお子さんの思考や個性を決めつけない姿勢は、メタ認知能力を育てるうえで重要です。決めつけてしまうと、子どもたちが自分を否定したり本心に気づかなかったりして、適切なメタ認知が困難になる可能性があります。
保護者様がお子さんに言葉をかける際は、以下の例を参考にしてメタ認知能力を高める言葉に変えていきましょう。
保護者様が「〇〇のほう」を提案したい場合でも、お子さんの思考や個性を尊重する姿勢を保ちましょう。

メタ認知能力を伸ばすためには、ほかの能力と関連づけて育成しましょう。それぞれの能力が相乗的に育ち、お子さんの成長を促進します。ここでは、メタ認知の向上に関連する能力として4つ紹介します。
自己観察力とは自分自身を客観的に見つめる能力を指し、感情的になったときに「今、私は〇〇の状態だ」と冷静に捉えることです。その感情がどこから来るのか考えることで、自分自身をより深く理解し、適切な行動へとつなげられます。
この過程でメタ認知能力が高まり、自己理解によって課題や欠点を改善するための行動を探ることが可能になるでしょう。たとえば「怒りの感情が湧いたときは深呼吸しよう」という具体的な行動につなげられます。行動の結果について再び自己観察すれば、メタ認知能力をさらに高められます。
メタ認知能力とは、自己の能力や傾向などを第三者の立場でモニタリングできる力を指します。的確な自己観察は、具体的な目標設定や計画策定を可能にします。
たとえば「私は英語が苦手だ」と自分の弱点を理解し、メタ認知を発揮して「英語の何が苦手なのか」を分析するとしましょう。ここで苦手を克服するための目標や計画を立てることが重要です。「語彙数が少ない」と認識すれば「平日5個ずつ覚えて土日に25個復習しよう」といったプランを立てられるかもしれません。
実際にやって改善点を見つけ、目標と計画を設定し直すなど、メタ認知能力をフルに稼働させながら鍛えていくことが可能です。
問題発見力や問題解決力もメタ認知能力と関連のあるスキルです。メタ認知能力とは自己の能力を客観的に見て評価する力を指し、その過程で強みや弱みなどの発見が生まれます。
弱点がわかれば克服するための方法を考える機会を得るでしょう。たとえば、メタ認知能力を活用して、以下のような流れで問題発見や問題解決力を発揮します。
このような思考の流れを作ることで「怒りっぽい」といった弱点を少しずつ克服していくのです。問題を見つけて解決する道のりは、メタ認知能力の強化につながります。
メタ認知とは知識や技能といった側面だけでなく創造力の育成につながる要素です。メタ認知を通じて自分の感情や思考を別の角度で見るのは、事物や事象、他者の考えなどを多面的な見方で捉えることにつながります。
メタ認知能力が低い場合「自分の思考=相手の思考」と決めつけてしまうため、多様な見方や考え方に気づきにくくなるでしょう。メタ認知能力があれば、相手の意見を参考にしながら新たな方法を導き出したり、まったく別の方法を試してみたりするなど創造性を発揮できます。

メタ認知は感情のコントロールや失敗の分析、現実的な目標の立て方など、子どもたちの成長に不可欠な要素が凝縮されています。
メタ認知が高まれば、子どもたちは自分に合った学習計画を立て、異なる価値観をもつ友だちとも関係を築きやすくなるでしょう。また、勉強やスポーツにおいてコツコツと努力を積み重ね、成果を上げることが可能です。
保護者様はメタ認知を高める方法や関連する能力に注意を払い、子どもたちの成長をサポートしましょう。「プロクラ」では、親しみやすくわかりやすいスタイルで子どもたちへの教育を提供しています。メタ認知能力の育成をめざす習い事として、ぜひご検討ください。
COLUMN